本記事では、接客業で頻繁に直面する「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と「正当なクレーム」の違いについて解説します。
両者の線引きや特徴、適切な対応方法、そして法的観点からの対策まで、実例を交えながら徹底的に分析します。職場での対応マニュアル作成や、スタッフ教育の参考にしていただける内容になっています。
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
カスタマーハラスメント(略して「カスハラ」)とは、顧客や利用者が企業や店舗の従業員に対して行う、理不尽なクレームや要求、暴言、脅迫など、精神的・肉体的な苦痛を与える行為のことを指します。
近年、このカスハラという言葉は広く認知されるようになり、社会問題として取り上げられることが増えてきました。カスハラの本質は、商品やサービスの品質改善を目的としたものではなく、相手を傷つけたり、自分の優位性を示したりすることが主な目的である点に特徴があります。
カスハラの特徴としては、以下のようなものが挙げられます:
- 明らかに過剰な要求や理不尽な主張
- 脅迫や恫喝を伴う言動
- 長時間の拘束や繰り返しの要求
- 個人を特定した攻撃や中傷
- セクハラ的な言動や差別的発言
カスハラは単なる不満の表明とは異なり、相手の人格や尊厳を傷つける行為であり、時には法的に問題となるケースもあります。接客業に従事する方々の精神的健康を著しく損なうことがあるため、適切な対応と防止策が求められています。
クレームとカスハラの明確な違い

クレームとカスハラは一見似ているように思えますが、その本質と目的には明確な違いがあります。
クレームの本質は、商品やサービスに対する正当な不満や改善要求です。顧客が期待していたものと実際に提供されたものとの間にギャップがあった場合に発生します。クレームを通じて、企業はサービス向上のきっかけを得ることができるため、ビジネス改善の重要な機会と捉えることができます。
一方、カスハラの本質は、相手を威圧し、精神的に追い詰めることにあります。商品やサービスの改善を目的としているわけではなく、時には特定の従業員を標的にした嫌がらせや、何らかの不当な利益を得ようとする行為につながることもあります。
両者の違いを具体的に整理すると:
| クレーム | カスハラ |
|---|---|
| 商品・サービスの改善が目的 | 相手を威圧・攻撃することが目的 |
| 具体的な問題点の指摘 | 感情的な攻撃や人格否定 |
| 解決策の提案や要望 | 非現実的な要求や脅迫 |
| 冷静な態度で伝えられることが多い | 声を荒げたり、暴言を吐いたりする |
| 企業活動の改善につながる | 従業員の心身の健康を害する |
クレームとカスハラを見分ける重要なポイントは、「その主張や要求に合理性があるか」「対応や解決策に納得する余地があるか」という点です。
真摯に対応しても一切妥協せず、理不尽な要求を続ける場合は、カスハラの可能性が高いと言えるでしょう。
正当なクレームの特徴と対応方法
正当なクレームには、特徴的なパターンがあります。これらを理解することで、適切な対応が可能になります。
正当なクレームの特徴
正当なクレームには、以下のような特徴があります:
- 具体的な問題点の指摘:「このようなサービスを期待していたが、実際には〇〇だった」といった具体的な内容です。
- 合理的な要求:問題解決のための妥当な要求や提案を含んでいます。
- 事実に基づいている:感情的な主張ではなく、実際に起こった出来事に基づいています。
- 改善の余地がある:指摘された問題点が、実際にサービスや商品の改善につながる可能性があります。
- 対話の余地がある:適切な説明や対応により、相互理解に至る可能性があります。
正当なクレームは企業にとって貴重なフィードバックとなり、サービス品質向上のきっかけとなります。こうした建設的なクレームを適切に処理することで、顧客満足度を高め、企業イメージの向上にもつながります。
正当なクレームへの効果的な対応方法
正当なクレームに対しては、以下のようなステップで対応することが効果的です:
- 傾聴と共感:まずは顧客の話を最後まで聞き、その気持ちに共感します。「ご不便をおかけして申し訳ありません」などの言葉で理解を示しましょう。
- 事実確認:具体的な状況を確認し、問題の本質を把握します。「いつ、どこで、何が、どのように」という基本情報を整理します。
- 原因究明と説明:問題が発生した原因を特定し、顧客に分かりやすく説明します。専門用語を避け、誠実に対応することが重要です。
- 解決策の提案:状況に応じた適切な解決策を提案します。可能な範囲で選択肢を示すことで、顧客の納得感が高まります。
- 迅速な対応:約束した対応は速やかに実行し、進捗状況を適宜報告します。
- 再発防止:同様の問題が起きないよう、社内で情報共有し、必要な改善策を講じます。
正当なクレームへの対応は、単なる問題解決にとどまらず、顧客との信頼関係を強化する機会です。誠実で迅速な対応により、不満を抱いていた顧客が、むしろロイヤルカスタマーへと変わることも少なくありません。
カスハラと認定される行為と事例
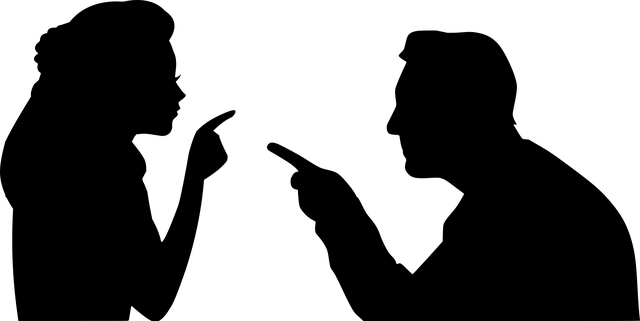
カスタマーハラスメントは多岐にわたりますが、一般的に以下のような行為がカスハラと認定されます。
カスハラと認定される典型的な行為
- 暴言・侮辱:「無能」「バカ」などの人格を否定する発言や罵倒
- 脅迫・恫喝:「上司を呼べ」「訴えるぞ」「SNSで拡散する」などの脅し
- 過剰な要求:明らかに常識を超えた補償や対応の要求
- 長時間拘束:同じ内容を延々と繰り返し、業務を妨害する
- 差別的言動:性別、年齢、国籍などに基づく差別的な発言
- セクハラ的言動:外見に関する不適切なコメントや性的な発言
- 個人攻撃:特定の従業員を名指しで非難し続ける行為
- 威圧的態度:大声を出す、机を叩く、詰め寄るなどの威圧行為
- SNS等での誹謗中傷:事実と異なる情報を拡散する行為
これらの行為は、相手の尊厳を傷つけ、精神的苦痛を与えるものであり、接客業に従事する方々の心身の健康に深刻な影響を及ぼすことがあります。
実際のカスハラ事例
事例1:飲食店での過剰要求 客が料理の味に不満を持ち、「全額返金してさらに慰謝料を払え」と大声で要求。店側が丁寧に対応しても一切妥協せず、「社長を呼べ」と3時間以上店員を拘束した。
事例2:小売店での威圧行為 商品の返品を申し出た際、店のポリシーで対応できないと説明されると、「お前のせいで子供が泣いている」「こんな店二度と来ない」と大声で叫び、他の客の前で店員を侮辱した。
事例3:コールセンターでの執拗な攻撃 サービス内容に不満を持った顧客が、同じオペレーターに対して毎日のように電話をかけ、「お前の名前と社員番号を言え」「お前のせいで迷惑している」と個人攻撃を繰り返した。
事例4:医療機関での不当な要求 診察の待ち時間に不満を持った患者が、「税金で働いているんだから、すぐに診ろ」と大声で騒ぎ、他の患者や看護師に対して暴言を吐いた。
これらの事例に共通するのは、問題解決を目的としていないという点です。カスハラの特徴は、相手への攻撃性や威圧的な態度、そして合理的な解決策を受け入れない頑なな姿勢にあります。
企業や組織は、このようなカスハラ行為から従業員を守るための明確な方針と対応策を持つことが重要です。次の項目では、そうした対応策について詳しく解説します。
クレーム対応でNGな言葉と対応
クレーム対応において、状況を悪化させてしまう言葉遣いや対応があります。これらを避け、適切な対応を心がけることが重要です。
クレーム対応でのNGワード
以下の言葉や表現は、顧客の不満を増幅させる可能性が高いため、使用を避けるべきです:
- 「できません」「無理です」:断定的な拒否の言葉は顧客の反感を買います。代わりに「〇〇の理由により、現状では難しいのですが、代替案として…」と提案を添えましょう。
- 「それは当社の規定です」:規定を盾に対応を拒むと、「顧客目線がない」という印象を与えます。「お客様のご要望に沿えるよう、規定の範囲内でできる限りの対応を…」といった表現が望ましいです。
- 「担当者が不在です」:責任回避と捉えられる可能性があります。「担当者は現在不在ですが、私がお話を承り、必ず担当者に伝えます」と対応しましょう。
- 「他のお客様はそのようなことを言われません」:比較による反論は、顧客を否定していると感じさせます。個々の状況に合わせた対応を心がけましょう。
- 「それはお客様の勘違いです」:直接的な否定は対立を生みます。「ご説明が不十分だったかもしれません」と自社の責任も認める姿勢が大切です。
効果的なクレーム対応のための言葉遣い
反対に、次のような表現はクレーム対応を円滑にします:
- 「ご不便・ご心配をおかけして申し訳ございません」:まずは顧客の気持ちに寄り添う言葉で共感を示します。
- 「確認させていただきます」:問題解決に向けた具体的な行動を示します。
- 「〇〇のご提案は可能です」:できることを明確に伝え、建設的な対話を促します。
- 「いただいたご意見は、今後のサービス改善に活かします」:顧客の声を重視していることを伝えます。
- 「お時間を頂戴できれば、詳しく調査いたします」:誠実な対応の姿勢を示します。
避けるべき対応パターン
言葉遣いだけでなく、以下のような対応パターンも避けるべきです:
- 機械的な対応:マニュアル通りの言葉だけを繰り返す対応は、「話を聞いていない」という印象を与えます。
- 責任転嫁:「これは本社の方針なので」など、他部署や他者に責任を転嫁する対応は信頼を損ないます。
- 約束の不履行:「折り返しご連絡します」と言ったにもかかわらず連絡しないことは、問題をさらに悪化させます。
- 感情的な反応:顧客が感情的になっても、対応する側は冷静さを保つことが重要です。
クレーム対応では、言葉遣いや態度が問題解決の鍵となります。否定的・防衛的な対応ではなく、顧客の立場に立った共感的な対応を心がけることで、多くの場合、状況を好転させることができます。
ただし、これはあくまで正当なクレームに対する対応であり、明らかなカスハラに対しては、次の項目で説明する対処法が必要になります。
カスハラへの適切な対処法

カスタマーハラスメントに直面した際、その場での適切な対応と、組織としての対策が重要です。ここでは、カスハラへの効果的な対処法を紹介します。
カスハラに直面した際の基本姿勢
- 冷静さを保つ:相手が感情的になっても、こちらは冷静さを失わないことが重要です。深呼吸をして、感情をコントロールしましょう。
- 安全確保を最優先:身の危険を感じる場合は、その場から離れるか、同僚や上司、必要に応じて警備や警察の応援を要請しましょう。従業員の安全は何よりも優先されるべきです。
- 一人で抱え込まない:カスハラは一人で対応すべき問題ではありません。必ず上司や同僚に状況を共有し、組織として対応する体制を整えましょう。
カスハラ撃退のための具体的テクニック
1. 毅然とした態度で対応する
カスハラ行為に対しては、「申し訳ありませんが、そのようなお話し方では対応できかねます」と毅然とした態度で伝えることが効果的です。謝罪や譲歩を繰り返すことで、かえって状況が悪化することもあります。
2. 録音・記録を行う
可能であれば、会話を録音したり、やり取りの記録を残したりすることが有効です。事前に「対応品質向上のため、会話を録音させていただきます」と告げておくことで、相手の行動を抑制する効果も期待できます。
3. 複数人での対応
カスハラが予想される場合は、最初から複数人で対応することが望ましいです。証人がいることで、相手の行動が抑制されるだけでなく、後々のトラブル防止にもなります。
4. 明確な対応限度を設ける
「このままでは対応を続けることができません」「○分経ちましたので、この件はいったん終了させていただきます」など、対応の限度を明確に示すことも重要です。無制限に対応を続けることは、業務にも支障をきたします。
5. 上位者への引き継ぎ
「上司を呼べ」という要求に対しては、必ずしも応じる必要はありませんが、状況によっては上位者に引き継ぐことで解決する場合もあります。ただし、これが常態化すると現場の権限が弱まるため、慎重な判断が必要です。
組織としての対応策
1. 明確なガイドラインの策定
カスハラに対する組織としての対応方針を明確にし、全従業員に周知することが重要です。「どのような行為がカスハラに該当するか」「どの段階でどう対応するか」などを具体的に示したガイドラインを作成しましょう。
2. 定期的な研修の実施
カスハラへの対応スキルを向上させるための研修を定期的に行うことが効果的です。ロールプレイなどを通じて、実践的な対応力を身につけることができます。
3. サポート体制の整備
カスハラを受けた従業員のための心理的ケアや相談窓口を設置するなど、サポート体制を整えることも重要です。一人で抱え込まず、組織として問題に取り組む姿勢を示しましょう。
カスハラへの対応は、個人の対応力だけでなく、組織としての体制づくりが鍵となります。従業員を守る明確な方針と、それを実行するための具体的な手順を整備することで、カスハラによる被害を最小限に抑えることができるでしょう。
カスハラを防ぐための組織的な取り組み
カスタマーハラスメントを未然に防ぎ、発生した場合の影響を最小限に抑えるためには、組織全体での取り組みが不可欠です。以下に、効果的な組織的対策を紹介します。
予防的アプローチ
1. 明確な企業方針の策定と公表
カスハラを許容しない企業姿勢を明確にし、店舗やウェブサイトなどで公表することが効果的です。例えば「当社では、従業員への暴言・暴力・過度な要求等のハラスメント行為はお断りしております」といった掲示を行うことで、カスハラ行為の抑止効果が期待できます。
2. 顧客への適切な期待値設定
サービス内容や対応範囲、所要時間などについて、事前に顧客に正確な情報を提供することで、認識のズレによるトラブルを防ぐことができます。特に、サービスの限界や制約条件については、丁寧な説明を心がけましょう。
3. 従業員教育の充実
定期的な研修を通じて、以下のスキルを従業員に身につけさせることが重要です:
- クレームとカスハラを見分ける判断力
- 初期段階でのエスカレーション防止テクニック
- 適切なコミュニケーションスキル
- 心理的負担への対処法
組織体制の整備
1. サポート体制の構築
カスハラ対応専門のチームや担当者を設置し、現場の従業員が一人で対応しなくても済むような体制を整えましょう。また、心理カウンセラーとの連携など、精神的ケアの仕組みも重要です。
2. 報告・記録システムの整備
カスハラ事案を漏れなく記録し、分析するためのシステムを構築しましょう。どのような状況でカスハラが発生しやすいかを把握することで、予防策の改善につなげることができます。
3. エスカレーションルートの明確化
現場の従業員がどの段階で上司や専門チームに引き継ぐべきかの基準を明確にし、迅速な対応ができる体制を整えましょう。
環境・システム面での対策
1. 物理的環境の整備
カウンターの高さや幅、監視カメラの設置、非常ボタンの配置など、物理的な環境を工夫することで、カスハラ行為の抑止や迅速な対応が可能になります。
2. デジタル対策の導入
オンラインでのカスハラ対策として、以下のような取り組みが効果的です:
- AIによる不適切なコメントの自動検出・フィルタリング
- オンラインサポートでの時間制限の設定
- チャットボットの活用による初期対応の自動化
3. 顧客フィードバックシステムの改善
適切なフィードバック手段を提供することで、顧客の不満が過度に高まる前に対応できるようにしましょう。簡単なアンケートや評価システムの導入が効果的です。
業界・社会全体での取り組み
カスハラ問題は一企業だけの問題ではなく、業界全体、さらには社会全体で取り組むべき課題です。同業他社との情報共有や、業界団体での共同宣言、社会啓発活動への参加なども検討しましょう。
カスハラ対策は、単なる従業員保護にとどまらず、健全な顧客関係の構築と企業価値の向上につながります。組織としての明確な方針と体系的な取り組みにより、すべての関係者にとって良好な環境を作り出すことが可能になるでしょう。
カスハラとパワハラの違い

カスタマーハラスメント(カスハラ)とパワーハラスメント(パワハラ)は、どちらもハラスメントの一種ですが、その性質や背景には重要な違いがあります。両者を正しく理解することで、それぞれに適した対策を講じることができます。
基本的な違い
主体と関係性の違い
カスハラとパワハラの最も基本的な違いは、ハラスメントを行う主体と、両者の関係性にあります。
- カスハラ:顧客(消費者)から従業員への一方的なハラスメント。基本的には取引関係にあり、直接の上下関係はありません。
- パワハラ:職場内での優越的な地位にある者から、部下や同僚などへのハラスメント。明確な上下関係や権力関係が存在します。
法律上の位置づけ
- パワハラ:2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、企業に防止措置が義務付けられています。法律上の定義も明確に存在します。
- カスハラ:現時点では、カスハラを直接規制する法律は存在しません。ただし、悪質な場合は暴行罪や脅迫罪など他の法律で対応される可能性があります。
行為の特徴と背景
発生要因の違い
- カスハラ:「お客様は神様」という考え方や、SNSでの拡散への恐れなどから、顧客の理不尽な要求にも応じてしまう企業文化が背景にあることが多いです。
- パワハラ:職場の権力構造や、成果主義の偏った解釈、コミュニケーション不足など、組織内の問題が背景にあることが多いです。
表出形態の違い
カスハラとパワハラは、具体的な行為としては類似点もありますが、以下のような特徴の違いがあります:
- カスハラ:一度きりの接触での突発的な行為が多く、SNSでの拡散や評判の低下を匂わせるなど、消費者としての優位性を利用した脅しが特徴的です。
- パワハラ:継続的・反復的な行為が多く、業務上の指導との境界が曖昧なことがあります。人事評価への影響など、組織内の権力を背景にした行為が特徴的です。
対応方法の違い
組織的対応の違い
- カスハラへの対応:顧客との関係性を考慮しつつも、従業員を守るための明確な基準設定と、必要に応じた毅然とした対応が重要です。場合によっては取引拒否も検討します。
- パワハラへの対応:内部通報制度の整備や第三者委員会の設置など、被害者が安心して相談できる体制づくりが重要です。加害者とされる上司等の公平な調査と教育も必要です。
法的対応の違い
- カスハラへの法的対応:悪質な場合は、業務妨害や名誉毀損、暴行・脅迫など、個別の犯罪として対応することになります。
- パワハラへの法的対応:パワハラ防止法に基づく企業の義務不履行として、行政指導の対象となることがあります。また、民事上の損害賠償請求の根拠にもなります。
共通点と対策の重なり
カスハラとパワハラは異なる現象ですが、人の尊厳を傷つける行為という本質は共通しています。また、対策にも共通点があります:
- 明確なガイドラインの策定
- 定期的な研修と啓発
- 相談窓口の設置
- 被害者のケア体制の整備
- 記録と報告の仕組み作り
これらの共通の対策を基盤としつつ、それぞれの特性に応じた対応策を講じることが、効果的なハラスメント対策につながります。
カスハラとパワハラ、それぞれの特性を理解し、適切な対策を講じることで、すべての関係者にとって健全な環境を築くことができるでしょう。
カスハラ被害から身を守るための法的措置
カスタマーハラスメントが深刻化した場合、法的手段を検討することも重要です。ここでは、カスハラ被害から従業員と企業を守るための法的措置について解説します。
カスハラに適用される可能性のある法律
現在、日本ではカスハラを直接規制する法律はありませんが、行為の内容によっては以下の法律が適用される可能性があります:


